1. はじめに|吃音に悩んでいるあなたへ
私は23歳まで、言葉が詰まることに苦しみながら、なんとか日々を乗り越えてきました。
このブログを書こうと思ったのは、「同じ悩みを持つ方に、少しでも希望を感じてもらえたら」 という気持ちがあるからです。
こんな方に読んでほしい:
- 吃音に悩んでいる人
- 言葉の詰まりで生きづらさを感じている人
- 周囲に吃音のある人がいて理解を深めたい人
2. 吃音とは?基本的な症状と原因
吃音は主に「連発」「伸発」「難発」などの種類がありますが、私の場合は「連発型」が強く出ていました。
たとえば「え、え、え、え〜と」のように、言葉の始まりを何度も繰り返してしまいます。
症状が出始めた頃
小学1年生のある日、急に言葉が出なくなりました。学校の友達や先生、さらには両親にすら話しづらくなり、気づけば心を閉ざすようになっていました。
原因・きっかけ
両親や先生は、「兄弟喧嘩でのストレスが原因かもしれない」 と言っていましたが、はっきりと断定はできません。ただ、この頃から毎日が息苦しく、孤独を深めていったのを覚えています。
3. 幼少期〜学生時代:言葉が出ない恐怖と孤独
小学校での辛いエピソード
国語の授業がとにかく苦痛でした。順番に当てられるたび、胸が高鳴って汗ばみ、いざ自分の番になると声が出ない。「喋る前からすでに辛い」 という状態でした。
周りとの距離
周囲は普通にできるのに、自分だけが当たり前に話せない——そのコンプレックスから、人と関わることが怖くなりました。
「どうせ話せないなら、はじめから話さないでおこう」
そう思うようになり、私の心の中には「話す自分」「話さない自分」の2人が存在していた気がします。
友達関係と孤独
学校で一緒に遊ぶ友達はいても、放課後に誘い合う仲間はいませんでした。
自分の言葉が思い通りにならない frustration と、自己否定感が常に付きまとい、「普通に話せない自分はダメだ」 と責め続けていました。
4. 中学・高校時代:隠す努力と限界
話さないことで自分を守る
クラスメイトとは必要最低限のやり取りだけ。休み時間に一人でいるといじめの対象になりそうなのでグループには所属するものの、自分からはほとんど話さず、なんとかやり過ごしていました。
言葉選びへの過剰な意識
「ここでこの言葉を言うと詰まってしまうかも…」という不安から、言い回しを必死で変えるものの、うまく伝わらないもどかしさに苛立つ日々。
誰にも相談できなかった理由
当時はまだネットも普及しておらず、「吃音」という言葉すら知らない状態。
ただ自分が「話せない」という現実だけがのしかかり、「一生このままなのかもしれない」「誰に相談しても変わらない」 と諦めてしまっていました。
限界を感じた瞬間
日常会話だけでなく、就職や進学のための面接が何よりも恐怖でした。
先生が練習に付き合ってくれても、言葉が出ない自分が情けなくて、右太ももを叩き続けてどうにか声を出そうとする——。そんな自分が嫌で仕方ありませんでした。
5. 吃音と本気で向き合ったきっかけ
高校時代の一冊の本
図書館で何気なく手に取った喜多川泰さんの『手紙屋』 という小説が、私の人生を大きく変えました。
「まずは行動してみよう」というメッセージに背中を押され、日記を書き始めたのです。
- 今日は喋れたとき、どんな気持ちだったか
- 今日は喋れなかったとき、何が原因だったか
こうやって振り返るうちに、「無意識で話している時は詰まりにくい」 と気づき、少しだけ希望を感じられました。
彼女が欲しい気持ちが勇気をくれた
社会人になってから「彼女が欲しい!」という思いで、思い切って合コンへ。2万円しかない中で5,000円を使うからには、一言も話せず終わりたくない——その必死さが、言葉を出す原動力になりました。
「吃音をなくす」から「共に生きる」へ
27歳以前の私は、吃音が出ないように常に身構えていました。しかし、工場勤務で人との会話が減り、心に少しゆとりが生まれたことで、「吃音も個性かもしれない」 と考えられるようになりました。苦しい時期が長かったからこそ、こう思えたのかもしれません。
6. 私が実践した克服・向き合い方
特別な発声練習はしなかった
実は呼吸法や発声練習は特にしていません。右太ももを叩きながら言葉を紡ぎ出すくらいでした。
吃音であることを公言しないまま
吃音があると伝えたら、馬鹿にされるのではないか。そう思って、これまで自分から「吃音持ちです」と話したことはありませんでした。
マインドセットの変化
「吃音は個性」と思いはじめてから、不思議と心が楽になりました。以前のように自分を責め続けることが減り、気持ちに少しだけ余裕が生まれました。
失敗したら早めに寝る
言葉が出ずに失敗してしまう日は、どうしても落ち込んでしまいます。そんな時は早めに布団に入り、眠ってしまうことが私のリセット方法でした。
7. 今振り返って思うこと
吃音は「消すべきもの」ではなく「自分の一部」
『嫌われる勇気』で、赤面症が告白を避ける理由に使われている話を読み、同じように吃音も自分を守るための仕組みなのかもしれない と思うようになりました。
完治を目指さなくてもいい
かつては「治らなきゃ生きていけない」と思っていましたが、そうではありませんでした。完治しなくても大丈夫だと認めた時、ようやく肩の力が抜けて、「今の自分」として生きやすくなりました。
19年間の葛藤が無駄じゃなかった瞬間
SNSで「吃音グループ」を見つけ、オフ会に参加した時のこと。怖さもありましたが、同年代の人たちと話すうちに、「吃音のままでも理解してくれる仲間はいるんだ」 と感じられたのは、大きな収穫でした。
8. 同じ悩みを抱えている人へのメッセージ
「苦しい時は逃げていい」
吃音が辛くて、何もしたくない時期は無理しなくて大丈夫。私は会話も仕事も逃げながらなんとか生き延びてきました。
大切なのは、「吃音を責めないであげること」。吃音を友達のように捉えて、一緒に生きていくスタンスもアリだと思います。
「あなたの価値は言葉だけで決まらない」
話せなくても、仕事で結果を出すことや自分らしく生きることは可能です。特にネットやチャットで完結する環境では、吃音のハンデを感じにくい場面も増えてきています。
どうしても辛い時は行政や医療機関を頼ろう
私は精神科に通い、薬の力を借りた時期もありました。行政の障がい福祉課で相談し、生活面のサポートを受けたこともあります。「助けを求めること」は、何も恥ずかしいことではありません。
9. サポート情報
- 役所の障がい福祉課:生活サポートや福祉サービスの提供が受けられます
- 精神科・心療内科:カウンセリングや投薬治療も検討できます
- SNSやコミュニティサイト:吃音を持つ人たちとつながり、情報交換ができます
10. まとめ|吃音と19年向き合って得たもの
私が辿り着いた答え
19年間、吃音を憎んできました。しかし、「共に生きる」 と決めてから気持ちが少し軽くなりました。
- 苦しい時は、行政サービスや医療機関の力を借りる
- ネットやチャットなど、吃音の負担が少ない方法を選ぶ
- 同じ悩みを持つ仲間と出会えば、孤独は和らぐ
最後に、あなたへ問いかけたい
あなたは今、自分の声とどう向き合っていますか? そして、これからの未来でどんな関係を築いていきたいですか?
私は19年間、吃音を克服することだけを目指してきましたが、最終的には「共に生きる」 決断をしました。そこからは気持ちがラクになり、同じ境遇の仲間と出会い、行政や精神科のサポートを得ながら自分らしい生き方を見つけました。言葉が詰まっても、それが私の価値を否定する理由にはならない
——そう思えるようになったのです。あなたもどうか、自分の声を責めずに受け入れてあげてください。
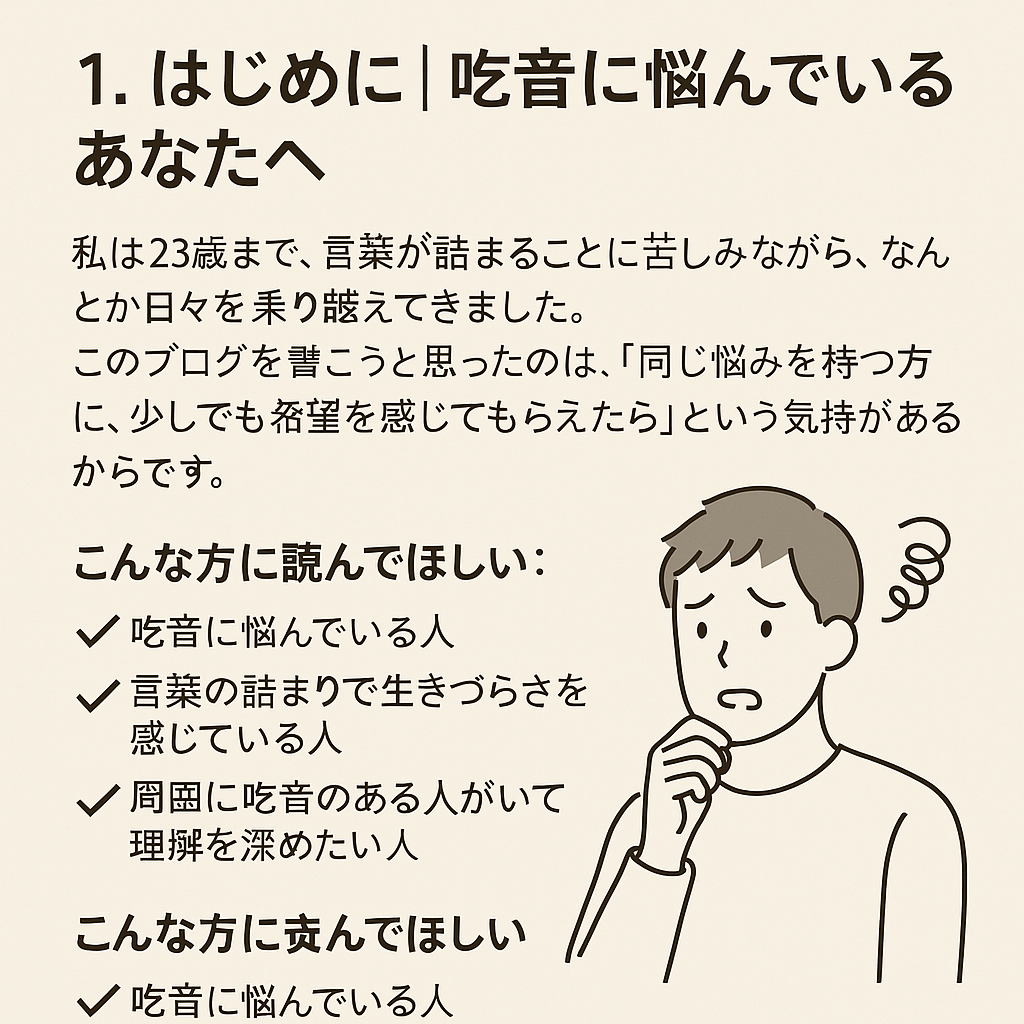


コメント