~自分らしく生きるための制度や支援をフル活用しよう~
はじめまして。私は現在30代で、これまで会社員として働いたのち、今は自分の会社を経営しています。
実は私は「吃音(きつおん)」を持っており、初対面の人が4人以上集まる場面だと、いまだに言葉が出づらくなることがあります。
昔は「こんな自分は社会に適応できない」と思い込み、心も体も限界ギリギリの状態で生きていました。しかし、いろいろな手段を試したり、精神科に行ったり、障害者手帳を取得したりする中で「できること」はたくさんある、と実感するようになりました。
今回は私の体験に基づき、
- 精神科の活用
- 自閉症スペクトラム症という診断
- 障害者手帳や障害年金など各種制度
- 就労支援やレジャー割引の利用方法
など、役立つ情報をできるだけわかりやすく整理してみました。この記事が、吃音や対人コミュニケーションの難しさに悩む方の心を少しでも軽くし、自分らしく生きるための「一歩」を踏み出すきっかけになれば幸いです。
✅ 目次
- 吃音と生きる私がまず伝えたいこと
- 精神科・心療内科の受診で得られる安心
- 自閉症スペクトラム症という診断がもたらした救い
- 障害者手帳・障害年金・各種福祉サービスの活用
- 会社へ「障害者」であることを伝えるメリットとハードル
- 就労移行支援・就労継続支援のススメ
- レジャーや交通、通信費の割引について
- 吃音を抱えた私の「乗り越え方」の工夫
- まとめ:あなたの未来はもっと広がる
1. 吃音と生きる私がまず伝えたいこと
私が吃音を自覚し始めたのは小さい頃でしたが、成長するにつれ症状が強まる時期と少しマシになる時期を繰り返しながらも、社会人になってからは「報・連・相」ができずに毎日のように怒られるという辛い経験をしました。そこで一番感じたのは、以下の2点です。
- 自分だけで抱え込むと限界が近づくのに気づかない
- 最初の一言さえ出ない状態は、本人にとって想像以上に苦しい
吃音を抱える人にしかわからないつらさや孤独感は、実際に声を出そうとしても出せないときに生まれます。「こんなに必死なのに出ないんだ…」という無力感は計り知れません。
ですが、その状態を変えるために使える手段やサポート体制は、私が思っていた以上に存在しました。ここからは、私自身が受けたり、知人が活用したりして「役立つ」と感じた情報をお伝えしていきます。
2. 精神科・心療内科の受診で得られる安心
🌙 夜眠れないほど悩む前に
社会人になったばかりのころ、私は会議で発言するのはもちろん、上司への報告さえ言葉が詰まってうまくできず、毎日「何やってるんだ!」と怒られていました。そのストレスで夜も眠れない日が続き、どんどん精神的に追い詰められていったのです。
そのときもっと早く精神科や心療内科に行っておけば、と思うことが何度もありました。実際、不眠症状や強い不安がある方は「薬でのサポート」を受けることで、いったん気持ちを落ち着かせられます。もちろん、薬だけで吃音や人間関係の悩みが根本から解決するわけではありませんが、酷い状況を少しだけでも和らげる役割は大きいです。
🏥 精神科での処方とカウンセリング
- 抗不安薬や睡眠薬:不安が強くて眠れない人にとっては助けになる場合が多い
- カウンセリングや認知行動療法(CBT):吃音への対処法や話し方の練習、思考のクセを見直す手がかりにもなる
最初の受診には勇気がいりますが、実際に行ってみると「もっと早く利用すればよかった」と思う方が多い印象です。
3. 自閉症スペクトラム症という診断がもたらした救い
🤔 相手が何を考えているか、わからない
私の場合、吃音があることで「相手は自分をどう見ているのだろう」と常に不安にかられていました。外に出るのも億劫になり、誰とも話せない日が続いたこともあります。そこで精神科に通い始めた結果、「自閉症スペクトラム症」という診断を受けました。
初めはショックでしたが、同時に「自分はおかしいわけではなく、脳の特性が違うだけなんだ」と理解できてからは、これまで感じていた罪悪感や恥ずかしさが少しだけ和らいだのです。吃音も含めて、生きづらさにはさまざまな要因が絡んでいる場合があります。早期に診断を受けると、適切なサポートや薬を利用する道が開けます。
4. 障害者手帳・障害年金・各種福祉サービスの活用
精神科で診断書をもらったら、市区町村の障がい福祉課で「障害者手帳」の申請や「訪問看護サービス」「障害福祉サービス利用」を申し込める可能性があります。私もいろいろ調べてみたところ、本当に多くの支援制度がありました。
📄 手帳や障害年金で得られるメリットを比較
| 項目 | 障害者手帳 | 障害年金 |
|---|---|---|
| 根拠となる法律 | 障害者総合支援法など | 公的年金制度 |
| 目的 | 生活面・社会参加のサポート | 生活費の補助(経済的保障) |
| 給付金 | なし(割引・減免などのサービスが中心) | 月額支給(1~3級などの区分) |
| 主なメリット | 税控除・交通機関やレジャー施設の割引等 | 収入源の確保 |
| 申請の難易度 | 比較的申請しやすい (医師の診断書必要) | 診断書に加え審査が厳しめ |
📝 障害者手帳の申請でできること
- 医療費の軽減(自立支援医療):精神科の診療費や薬代などが1割負担になる
- 公共交通機関の割引:バスや電車、飛行機が割引になる可能性あり
- 税金の控除:所得税・住民税・自動車税などが軽減される場合も
- 通信費の割引:大手キャリア(ドコモ・au・ソフトバンクなど)では基本使用料が安くなることあり
💰 障害年金の申請
「自閉スペクトラム症」などでも審査を通れば受給は可能ですが、日常生活が非常に困難なレベルであることなど一定の条件を満たさないと通りづらいのが現状です。ただ、「まずは申請してみる」こと自体は誰でもできます。結果がどうなるかは審査次第ですが、可能性を閉ざさないことが大切です。
5. 会社へ「障害者」であることを伝えるメリットとハードル
😣 大企業は障害者雇用の枠がある
法律で「一定以上の規模の会社は、一定割合の障害者を雇用しなければならない」と定められているため、企業によっては障害者雇用枠が埋まっていない場合があります。そこで、自分が障害者手帳を持っていると申告すると、企業から見ると「国に支払っている納付金を減らせるかもしれない」メリットがあるのです。
「会社に自分は障害者です」と言うのは大変な勇気がいります。ただ、上手くいけば職場での配慮を得やすくなったり、働きやすい環境を整えてもらえたりする利点があります。
⚠️ 直接交渉の難しさ
実際には部長クラスや人事担当と直接話をする必要がある場合が多く、吃音のある方にとっては「想像するだけで怖い」シチュエーションかもしれません。しかし、その壁を乗り越えると、
- 給与アップ交渉(納付金より少ない額で合意するなど)
- 仕事の進め方を柔軟に変えてもらう
- 周囲に吃音への理解を促してもらう
といったメリットが現実的になります。私自身は起業しましたが、もし当時の会社員時代にこうした制度を知っていれば、より早く楽になれたかもしれません。
6. 就労移行支援・就労継続支援のススメ
💼 就労移行支援
「一般企業で働きたいけど、まずはトレーニングが必要」という方におすすめです。最長2年間、以下のような支援を受けながら社会復帰を目指せます。
- パソコンの操作練習(Word、Excel、タイピングなど)
- コミュニケーション練習(あいさつ、報連相、電話応対など)
- 就職活動のサポート(履歴書・職務経歴書の書き方、面接練習)
🅰️ 就労継続支援A型
- 雇用契約を結ぶ
- 最低賃金以上の給料が支給される
- 社会保険に加入できる
A型は「一般就労と同じような扱いで働きたいが、いきなりフルタイムでバリバリは難しい…」という方におすすめです。
🅱️ 就労継続支援B型
- 雇用契約は結ばない(工賃制)
- 体調に波がある人でも無理なく続けやすい
- 作業内容は比較的軽め
B型は「自分のペースで社会参加したい」「あまり長時間働けない」という方に向いています。給料は低めですが、マイペースで働ける環境を得られるため、ステップアップの第一歩として選ぶ人も多いです。
7. レジャーや交通、通信費の割引について
🎉 レジャー施設の割引
- 映画館:障害者手帳提示で半額になるケースが多い
- テーマパーク:ディズニーランドやUSJなど、大手も対応
- 美術館・博物館:無料または割引になることあり
旅行や週末のレジャーを楽しみやすくなるのは、ストレス発散にも効果的です。
🚍 交通費の割引
- JR・私鉄・バス:手帳の等級によっては半額になる
- 飛行機:ANAやJALで約50%オフになる場合も
通院や出張、旅行をするときに大きな負担軽減となります。
📱 通信費の割引
- 大手キャリア(ドコモ・au・ソフトバンク):基本使用料の大幅割引
- 家族も適用になるケースあり
窓口で障害者手帳を提示するだけで割引が適用される場合もあるので、忘れずに問い合わせてみましょう。
8. 吃音を抱えた私の「乗り越え方」の工夫
ここまで制度や支援サービスについて述べてきましたが、吃音で日常的に苦しむ私自身が実践しているちょっとした工夫もシェアします。
- 最初のひと言が出ないときは、とにかく「声にならない声」を出す
- 口の中で「あ…」とだけ繰り返してみる
- 太ももを軽く叩いてリズムを取る(私のおまじないです)
- あらかじめシナリオを作って練習する
- 重要な電話や報告は、台本を作って音読しておく
- 緊張する場面ほど、事前のイメージトレーニングが効果的
- 周囲に「吃音がある」と言いやすい環境を作る
- 会社や学校に一度カミングアウトすると、相手が会話のペースを調整してくれることも増える
- 親しい友人には「言葉が詰まるかもしれないけど、待ってほしい」と伝えておく
- カウンセリングや自助グループを活用する
- 専門家や同じ吃音の仲間と悩みを共有すると「自分だけではない」と気づける
- ネット上のコミュニティやSNSで情報交換するのも有効
- できないことより、できることに目を向ける
- 吃音があってもSNSでの文章なら問題なく発信できる
- 人前で話すのが苦手でも、リモートやチャット主体の業務で力を発揮できるかもしれない
9. まとめ:あなたの未来はもっと広がる
吃音は、当事者にしかわからない苦しみがあります。一言を発するのにも大きなエネルギーが必要で、そのたびに「なんで自分はうまく話せないのだろう」と自分を責めてしまいがちです。
しかしながら、
- 精神科・心療内科で専門家に相談し、必要な治療やカウンセリングを受ける
- 障害者手帳や障害年金を検討し、生活面の負担を減らす
- 会社へのカミングアウトによって合理的配慮を得たり、給与や勤務形態を交渉する
- 就労移行支援・就労継続支援で段階的に慣れながら働く
- レジャー割引や交通費の軽減などを利用し、楽しみを見つける
これらの方法を組み合わせることで、驚くほど生きやすさが増すのです。
私が会社を経営する立場になって一番強く思うのは、「当事者の特性をしっかり理解し、能力を活かせる環境を作れば、優秀な人材がたくさんいる」ということです。吃音や自閉症スペクトラム症などの特性を持った方は、独特の集中力やアイデアを持っていることも珍しくありません。むしろ、多様な人たちが集まることが組織にプラスになると感じています。
👉 「声が出づらいから」といって、人としての価値が下がるわけでは決してない
👉 自分に合った働き方や支援策を知れば、ストレスや不安は必ず軽減できる
どうか、辛いときはひとりで悩まず、周囲や専門家、行政の力を借りてみてください。あなたが自分らしく生きるためのきっかけが、どこかに必ずあるはずです。そして、一歩踏み出すだけで状況は大きく変わる可能性があります。
これまで私が体験して得た知識と、仲間たちから教えてもらった制度やサービスが、いま苦しんでいる誰かの「少しだけでもラクになる」手助けになれば幸いです。あなたはあなたのままで、きっと大丈夫。今後の人生が、少しでも明るい道に繋がっていきますように。
<div style=”text-align: center;”> ✨ 最後までお読みいただき、ありがとうございました ✨ </div>

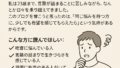
コメント